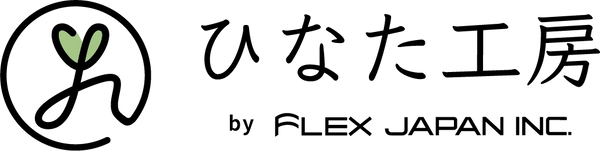ひなた短編文学賞結果発表
ひなた短編文学賞にたくさんのご応募ありがとうございました。
合計800作品を超えるご応募の中から、選考委員が厳正に選出した受賞作品を発表いたします。
主催者総評
フレックスジャパン株式会社
代表取締役社長 矢島隆生
ひなた短編文学賞は、福島第一原発のある双葉町に誕生した衣料品リメイクのアトリエ「ひなた工房」の開業を記念して創設しました。
東日本大震災と原発事故という未曾有の災禍を経て、いまも歩みを続けるこの町にとって、「再生」と「希望」はその姿を象徴する言葉です。
その思いを込めて、「生まれ変わる」をテーマに作品を募集してまいりました。
2022年に避難指示が解除された双葉町では、郵便局の再開、診療所の開設、スーパーの開業など、少しずつ生活の息吹が戻り、人々の営みが確かな形を取り戻しつつあります。
失われたものの大きさを抱えながらも、そこに新たな一歩を見出す姿は、まさに人間の力強さそのものです。
そこで第三回を迎える本年は、「あらたな一歩」を募集の追加テーマに掲げました。
変わらないように見える日常の中にも、誰かの決意や小さな変化が息づいています。
思い切って踏み出す瞬間、あるいは思いがけず訪れた転機――それらはすべて、人生の新たな章を開く「あらたな一歩」ではないでしょうか。
今回も全国各地から多くの作品をご応募いただきました。
ひとつひとつの物語が、それぞれに「生まれ変わり」や「あらたな一歩」を語ってくれました。
作品を通じてこの二つのテーマを言葉にし、形にしてくださった投稿者の皆さまに、心より敬意を表すと共にお礼申し上げます。
そして開催・運営にご協力くださった個人、企業、団体の皆さまにも、深く感謝申し上げます。
最後になりましたが、各賞を受賞された皆さまに心よりお祝い申し上げます。
誠におめでとうございます。
大賞
「あらたな色」
谷地雪
双葉町長賞
「どんな色が、好き?」
高橋 うによ
MFU賞
「遠まわりの雛たち」
上野美里
太田屋賞
「新しい壁」
高瀬 な奈
太田屋賞受賞作品は、副賞として受賞作品を原作とした映像が制作されました。ぜひご覧ください。
準大賞
「⻘いハンカチ」
ウダ‧タマキ
佳作
「ふたりぶん」
⾬宮球太
「父のパンツ」
にゃんしー
「いびつでも」
蒼い月
「未来と約束」
榊シュウ
「駄菓子屋「こゆき」」
敦子
「美術館の蒼」
市川とおる
「人の紡ぐ着物」
まつかほ
「⻘いセーター」
葉月樹
「灰のゆくさき」
吉田六
「三十一音の架け橋」
紫冬湖
「もう戻れない場所を、前と呼ぶ 」
Komta
「答辞」
蒼月 友
「遥か彼方の、にゃあ」
灯伊達蒔雪
「悲劇のヒロインのその先」
五香水貴
「練習」
才田道隆
「さぁ、この目に何をうつそうか」
吉沢藍
「あの空を広げて」
イチフジ
アイデア賞
「ブルーの私」
にいたかりんご
ティーンズ賞
「潮風の向こうで。」
いろは
選考通過作品
三次選考通過作品
受賞作を除く
三次選考を通過された作品の一覧を以下に掲載いたします。
惜しくも最終選考には至りませんでしたが、いずれも高い完成度と独自の表現力を備えた作品として評価されました。
「アルストロメリア」千栄
「りんごジャム」耕す太郎
「破けた道着と袖の音」太田風馬
「門出に咲く」げんのしょうこ
「イオ」二宮白黒郎
「風鈴の鳴るアパート」ミラク
「その先を知りたい」湯水こん
「リメルト‧ブルー」小石 創樹
「海を望むバンダナ」まちこ
「水引リースを編んだなら」長谷川彩香
「雪の中で咲く楓」月野 咲
「出窓のあたらしい物語」もりまりこ
「旅立つダルマ」藤上 一
「手放す」池内陽
「未来への祈り」ぴぴこ
「穂の香」上達 衣織
「つまづいたっていいじゃないか」山口ゆたか
「ステージはいつまでも」紫冬湖
「風の音が聞こえる場所」茂垣阿学
「青空の心友」芹川としや
「墓参り」小坂桃香
「記憶する線香」五香水貴
「あらたな景色」久保田毒虫
「魂の回数券」新木かおる
審査員総評
選考委員長
塚田浩司氏
小説家
受賞された皆様、おめでとうございます。
そして応募してくださった皆様、関わってくださったすべての方に感謝いたします。
今回のテーマは「あらたな一歩」です。生きていれば、日々の中で辛いことはたくさんあると思います。しかし、生きてさえいれば、誰でも「あらたな一歩」を踏み出すことができる。応募作品を読みながら、そんなことを思いました。
大賞作品と準大賞についてコメントしたいと思います。
「あらたな色」
主人公は不登校の娘をもつ母親です。派手な展開はないですし、最終的にも問題がすべて解決したわけではありません。
しかし、娘も、そして母親も、確実に新たな一歩を踏み始めていました。
優しさと救いのある素晴らしい作品でした。大賞受賞おめでとうございます。
「青いハンカチ」
冒頭の一行から引き込まれました。青いハンカチが、主人公の若き日の恋、夫婦の絆、さらには孫との交流に寄り添い、人間のドラマが詰まっていました。ラストにあたたかな気持ちになるのも心に響きました。
全体を見て、第3回にもなると賞のカラーというものが定着してきたなという印象です。過去2回と比べてカテゴリーエラーだと感じる作品は少なく、穏やかで優しい物語が多かったです。
それはポジティブな感想でもある反面、似た傾向の作品が増えたとも感じています。
そんな中、佳作に選ばれた作品には、少し目先の変わった作品が多かったように思います。
テーマを真正面から表現した作品も、少し遊び心を加えた作品も、どちらも素晴らしく、楽しませていただきました。
応募してくださった皆様、ありがとうございました。作家としても、とても刺激になりました。
選考委員
八木原保
一般社団法人日本メンズファッション協会(MFU)理事長
一般社団法人日本メンズファッション協会(MFU)は「感動創造」を理念に掲げ、事業活動を通じて社会貢献と豊かな生活文化の実現に取り組んでいます。
読者の皆さんの日々が元気になるような作品が集まることを願い「ひなた短編文学賞」を共催しています。
今年は主人公が「あらたな一歩」を踏み出すことに期待し「遠まわりの雛たち」をMFU賞に選びました。
「遠まわりの雛たち」
あらたな一歩には今日の挫折が切っ掛けになるかもしません。「人生万事塞翁が馬」あるいは「禍福は糾える縄の如し」を現実の世界でも実感されている人達は多いことと思います。
本作はそのような哲学的なモチーフにも拘わらず最後にはクスっと笑えるストーリーです。
お楽しみください。
選考委員
伊澤史朗氏
双葉町長
2023 年のフレックスジャパン株式会社ひなた工房の双葉町での開業を記念して創設された「ひなた短編文学賞」が、今年で 3 回目の開催の運びに至ったことを大変嬉しく思っています。
今回も多くの作品が応募され、執筆者の方々ならびに、本文学賞開催に関わったすべての方々に厚く御礼申し上げます。
「どんな色が、好き?」
「ママはね、ピンクが好き」、「ぼくはね、あおかな」という作者とお子さんとのやりとり。作者が若かった頃に世間からの見方に苦しんだ時期。
現在になり、息子さんとの素直な思いを言い合える関係。
好きなものを好きだといえること、それぞれの価値観が認められること、
その大事さを感じる作品でした。
選考委員
太田博久氏
株式会社太田屋 代表取締役社長
第三回ひなた短編文学賞にあたり、僭越ながら「太田屋賞」を設け選考委員を務めることとなりました。この文学賞の根底には「喪失と向き合い未来をつくる」という弊社が営む葬送供養と共通する思いが流れていると感じています。ご応募いただいたすべての作品を拝読し、選考に迷う作品が何点もございましたが、その中から「新しい壁」を受賞作品といたしました。亡き祖父と共に「あらたな一歩」を踏み出そうとする壁装職人の孫の姿を描いたこの作品は、多くのご遺族と接する弊社が、そのお一人お一人に叶えて欲しい姿そのものです。受賞作品をイラストで映像化いたしましたので、ご覧いただけましたら幸いです。(映像化作品は11月末公開予定)
選考委員
蜂賀三月氏
小説家
私たちの生活は「一歩」の連続です。
人の数だけ歩み方があるように、多種多様な作品が届きました。
内容の違いはあれど、どの作品も日向のようなぬくもりがありました。
ひなた短編文学賞の趣旨に寄り添っていただき、本当にありがとうございます。
作品を応募してくれた作家の皆様に、心から感謝を申し上げます。
過去最多となった応募作品の中から、大賞に輝いたのは谷地雪さんの『あらたな色』。
いじめが原因で不登校になった母娘の物語です。作品内で語られる「あらたな一歩」は、人によっては物足りないように感じるかもしれません。それでも、一歩は一歩です。どれだけ進んだかは些細な問題で、本当に大切なのは踏み出す行為そのものにあるように感じました。作品を読んだ人に、踏み出す勇気を与えてくれる傑作です。
続いて、準大賞に選出されたのはウダ・タマキさんの『青いハンカチ』。
ありありと情景が浮かび上がってくる文章に惹かれました。
しっかりと描写・表現されており、文章構成もよく整理されていて、物語が沁み込んでくるようでした。
人生において「あらたな一歩」を踏み出さなければいけない場面は、たくさん存在します。
ときには歩みが止まったり、後退することだってあるでしょう。
そうしたとき、自分のためだけじゃなくて誰かのために前を向こうとする尊さを、この作品が教えてくれました。
さて、第一回、第二回に続き、選考委員という立場で全作品を拝読いたしました。
ひなた短編文学賞は賞の特性上、辛い過去や悩みなど、人の心のセンシティブな部分にフォーカスを当てる作品がよく届きます。それはたくさんの人の痛みに触れるのと同じであり、小説というフィクションだとしても、真摯に向き合う覚悟が必要です。作品を読み進めていくなかで、今回は小説(ひなた短編文学賞)に挑戦する気持ちを題材にした作品がいくつかありました。ある意味メタ的な構造の小説ですが、ひなた短編文学賞自体が誰かの「あらたな一歩」になっていることを感じ、感銘を受けました。同時に、このひなた短編文学賞という文学賞が続いていく意味と意義について、深く考えさせられました。
痛みを受け入れることや、問題を乗り越えること。人や場所、記憶に寄り添うこと。そして、誰かの一歩を見守ること。「あらたな一歩」の形は人それぞれですが、どれも価値のあることです。惜しくも受賞を逃した方々の作品も、素晴らしいものばかりでした。可能ならば、ぜひ投稿サイトなどを活用してたくさんの人に届けていただきたいです。それが、誰かにとって、自分にとっての「あらたな一歩」に続くかもしれません。
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。
ひなた短編文学賞にたくさんのご応募ありがとうございました。
合計800作品を超えるご応募の中から、選考委員が厳正に選出した受賞作品を発表いたします。
主催者総評
フレックスジャパン株式会社
代表取締役社長 矢島隆生
ひなた短編文学賞は、福島第一原発のある双葉町に誕生した衣料品リメイクのアトリエ「ひなた工房」の開業を記念して創設しました。
東日本大震災と原発事故という未曾有の災禍を経て、いまも歩みを続けるこの町にとって、「再生」と「希望」はその姿を象徴する言葉です。
その思いを込めて、「生まれ変わる」をテーマに作品を募集してまいりました。
2022年に避難指示が解除された双葉町では、郵便局の再開、診療所の開設、スーパーの開業など、少しずつ生活の息吹が戻り、人々の営みが確かな形を取り戻しつつあります。
失われたものの大きさを抱えながらも、そこに新たな一歩を見出す姿は、まさに人間の力強さそのものです。
そこで第三回を迎える本年は、「あらたな一歩」を募集の追加テーマに掲げました。
変わらないように見える日常の中にも、誰かの決意や小さな変化が息づいています。
思い切って踏み出す瞬間、あるいは思いがけず訪れた転機――それらはすべて、人生の新たな章を開く「あらたな一歩」ではないでしょうか。
今回も全国各地から多くの作品をご応募いただきました。
ひとつひとつの物語が、それぞれに「生まれ変わり」や「あらたな一歩」を語ってくれました。
作品を通じてこの二つのテーマを言葉にし、形にしてくださった投稿者の皆さまに、心より敬意を表すと共にお礼申し上げます。
そして開催・運営にご協力くださった個人、企業、団体の皆さまにも、深く感謝申し上げます。
最後になりましたが、各賞を受賞された皆さまに心よりお祝い申し上げます。
誠におめでとうございます。
代表取締役社長 矢島隆生
ひなた短編文学賞は、福島第一原発のある双葉町に誕生した衣料品リメイクのアトリエ「ひなた工房」の開業を記念して創設しました。
東日本大震災と原発事故という未曾有の災禍を経て、いまも歩みを続けるこの町にとって、「再生」と「希望」はその姿を象徴する言葉です。
その思いを込めて、「生まれ変わる」をテーマに作品を募集してまいりました。
2022年に避難指示が解除された双葉町では、郵便局の再開、診療所の開設、スーパーの開業など、少しずつ生活の息吹が戻り、人々の営みが確かな形を取り戻しつつあります。
失われたものの大きさを抱えながらも、そこに新たな一歩を見出す姿は、まさに人間の力強さそのものです。
そこで第三回を迎える本年は、「あらたな一歩」を募集の追加テーマに掲げました。
変わらないように見える日常の中にも、誰かの決意や小さな変化が息づいています。
思い切って踏み出す瞬間、あるいは思いがけず訪れた転機――それらはすべて、人生の新たな章を開く「あらたな一歩」ではないでしょうか。
今回も全国各地から多くの作品をご応募いただきました。
ひとつひとつの物語が、それぞれに「生まれ変わり」や「あらたな一歩」を語ってくれました。
作品を通じてこの二つのテーマを言葉にし、形にしてくださった投稿者の皆さまに、心より敬意を表すと共にお礼申し上げます。
そして開催・運営にご協力くださった個人、企業、団体の皆さまにも、深く感謝申し上げます。
最後になりましたが、各賞を受賞された皆さまに心よりお祝い申し上げます。
誠におめでとうございます。
大賞
「あらたな色」
谷地雪
双葉町長賞
「どんな色が、好き?」
高橋 うによ
MFU賞
「遠まわりの雛たち」
上野美里
太田屋賞
「新しい壁」
高瀬 な奈
太田屋賞受賞作品は、副賞として受賞作品を原作とした映像が制作されました。ぜひご覧ください。
準大賞
「⻘いハンカチ」
ウダ‧タマキ
佳作
「ふたりぶん」
⾬宮球太
「父のパンツ」
にゃんしー
「いびつでも」
蒼い月
「未来と約束」
榊シュウ
「駄菓子屋「こゆき」」
敦子
「美術館の蒼」
市川とおる
「人の紡ぐ着物」
まつかほ
「⻘いセーター」
葉月樹
「灰のゆくさき」
吉田六
「三十一音の架け橋」
紫冬湖
「もう戻れない場所を、前と呼ぶ 」
Komta
「答辞」
蒼月 友
「遥か彼方の、にゃあ」
灯伊達蒔雪
「悲劇のヒロインのその先」
五香水貴
「練習」
才田道隆
「さぁ、この目に何をうつそうか」
吉沢藍
「あの空を広げて」
イチフジ
アイデア賞
「ブルーの私」
にいたかりんご
ティーンズ賞
「潮風の向こうで。」
いろは
三次選考通過作品
受賞作を除く
三次選考を通過された作品の一覧を以下に掲載いたします。
惜しくも最終選考には至りませんでしたが、いずれも高い完成度と独自の表現力を備えた作品として評価されました。
「アルストロメリア」千栄
「りんごジャム」耕す太郎
「破けた道着と袖の音」太田風馬
「門出に咲く」げんのしょうこ
「イオ」二宮白黒郎
「風鈴の鳴るアパート」ミラク
「その先を知りたい」湯水こん
「リメルト‧ブルー」小石 創樹
「海を望むバンダナ」まちこ
「水引リースを編んだなら」長谷川彩香
「雪の中で咲く楓」月野 咲
「出窓のあたらしい物語」もりまりこ
「旅立つダルマ」藤上 一
「手放す」池内陽
「未来への祈り」ぴぴこ
「穂の香」上達 衣織
「つまづいたっていいじゃないか」山口ゆたか
「ステージはいつまでも」紫冬湖
「風の音が聞こえる場所」茂垣阿学
「青空の心友」芹川としや
「墓参り」小坂桃香
「記憶する線香」五香水貴
「あらたな景色」久保田毒虫
「魂の回数券」新木かおる
審査員総評
選考委員長
塚田浩司氏
小説家
受賞された皆様、おめでとうございます。
そして応募してくださった皆様、関わってくださったすべての方に感謝いたします。
今回のテーマは「あらたな一歩」です。生きていれば、日々の中で辛いことはたくさんあると思います。しかし、生きてさえいれば、誰でも「あらたな一歩」を踏み出すことができる。応募作品を読みながら、そんなことを思いました。
大賞作品と準大賞についてコメントしたいと思います。
「あらたな色」
主人公は不登校の娘をもつ母親です。派手な展開はないですし、最終的にも問題がすべて解決したわけではありません。
しかし、娘も、そして母親も、確実に新たな一歩を踏み始めていました。
優しさと救いのある素晴らしい作品でした。大賞受賞おめでとうございます。
「青いハンカチ」
冒頭の一行から引き込まれました。青いハンカチが、主人公の若き日の恋、夫婦の絆、さらには孫との交流に寄り添い、人間のドラマが詰まっていました。ラストにあたたかな気持ちになるのも心に響きました。
全体を見て、第3回にもなると賞のカラーというものが定着してきたなという印象です。過去2回と比べてカテゴリーエラーだと感じる作品は少なく、穏やかで優しい物語が多かったです。
それはポジティブな感想でもある反面、似た傾向の作品が増えたとも感じています。
そんな中、佳作に選ばれた作品には、少し目先の変わった作品が多かったように思います。
テーマを真正面から表現した作品も、少し遊び心を加えた作品も、どちらも素晴らしく、楽しませていただきました。
応募してくださった皆様、ありがとうございました。作家としても、とても刺激になりました。
選考委員
八木原保
一般社団法人日本メンズファッション協会(MFU)理事長
一般社団法人日本メンズファッション協会(MFU)は「感動創造」を理念に掲げ、事業活動を通じて社会貢献と豊かな生活文化の実現に取り組んでいます。
読者の皆さんの日々が元気になるような作品が集まることを願い「ひなた短編文学賞」を共催しています。
今年は主人公が「あらたな一歩」を踏み出すことに期待し「遠まわりの雛たち」をMFU賞に選びました。
「遠まわりの雛たち」
あらたな一歩には今日の挫折が切っ掛けになるかもしません。「人生万事塞翁が馬」あるいは「禍福は糾える縄の如し」を現実の世界でも実感されている人達は多いことと思います。
本作はそのような哲学的なモチーフにも拘わらず最後にはクスっと笑えるストーリーです。
お楽しみください。
選考委員
伊澤史朗氏
双葉町長
2023 年のフレックスジャパン株式会社ひなた工房の双葉町での開業を記念して創設された「ひなた短編文学賞」が、今年で 3 回目の開催の運びに至ったことを大変嬉しく思っています。
今回も多くの作品が応募され、執筆者の方々ならびに、本文学賞開催に関わったすべての方々に厚く御礼申し上げます。
「どんな色が、好き?」
「ママはね、ピンクが好き」、「ぼくはね、あおかな」という作者とお子さんとのやりとり。作者が若かった頃に世間からの見方に苦しんだ時期。
現在になり、息子さんとの素直な思いを言い合える関係。
好きなものを好きだといえること、それぞれの価値観が認められること、
その大事さを感じる作品でした。
選考委員
太田博久氏
株式会社太田屋 代表取締役社長
第三回ひなた短編文学賞にあたり、僭越ながら「太田屋賞」を設け選考委員を務めることとなりました。この文学賞の根底には「喪失と向き合い未来をつくる」という弊社が営む葬送供養と共通する思いが流れていると感じています。ご応募いただいたすべての作品を拝読し、選考に迷う作品が何点もございましたが、その中から「新しい壁」を受賞作品といたしました。亡き祖父と共に「あらたな一歩」を踏み出そうとする壁装職人の孫の姿を描いたこの作品は、多くのご遺族と接する弊社が、そのお一人お一人に叶えて欲しい姿そのものです。受賞作品をイラストで映像化いたしましたので、ご覧いただけましたら幸いです。(映像化作品は11月末公開予定)
選考委員
蜂賀三月氏
小説家
私たちの生活は「一歩」の連続です。
人の数だけ歩み方があるように、多種多様な作品が届きました。
内容の違いはあれど、どの作品も日向のようなぬくもりがありました。
ひなた短編文学賞の趣旨に寄り添っていただき、本当にありがとうございます。
作品を応募してくれた作家の皆様に、心から感謝を申し上げます。
過去最多となった応募作品の中から、大賞に輝いたのは谷地雪さんの『あらたな色』。
いじめが原因で不登校になった母娘の物語です。作品内で語られる「あらたな一歩」は、人によっては物足りないように感じるかもしれません。それでも、一歩は一歩です。どれだけ進んだかは些細な問題で、本当に大切なのは踏み出す行為そのものにあるように感じました。作品を読んだ人に、踏み出す勇気を与えてくれる傑作です。
続いて、準大賞に選出されたのはウダ・タマキさんの『青いハンカチ』。
ありありと情景が浮かび上がってくる文章に惹かれました。
しっかりと描写・表現されており、文章構成もよく整理されていて、物語が沁み込んでくるようでした。
人生において「あらたな一歩」を踏み出さなければいけない場面は、たくさん存在します。
ときには歩みが止まったり、後退することだってあるでしょう。
そうしたとき、自分のためだけじゃなくて誰かのために前を向こうとする尊さを、この作品が教えてくれました。
さて、第一回、第二回に続き、選考委員という立場で全作品を拝読いたしました。
ひなた短編文学賞は賞の特性上、辛い過去や悩みなど、人の心のセンシティブな部分にフォーカスを当てる作品がよく届きます。それはたくさんの人の痛みに触れるのと同じであり、小説というフィクションだとしても、真摯に向き合う覚悟が必要です。作品を読み進めていくなかで、今回は小説(ひなた短編文学賞)に挑戦する気持ちを題材にした作品がいくつかありました。ある意味メタ的な構造の小説ですが、ひなた短編文学賞自体が誰かの「あらたな一歩」になっていることを感じ、感銘を受けました。同時に、このひなた短編文学賞という文学賞が続いていく意味と意義について、深く考えさせられました。
痛みを受け入れることや、問題を乗り越えること。人や場所、記憶に寄り添うこと。そして、誰かの一歩を見守ること。「あらたな一歩」の形は人それぞれですが、どれも価値のあることです。惜しくも受賞を逃した方々の作品も、素晴らしいものばかりでした。可能ならば、ぜひ投稿サイトなどを活用してたくさんの人に届けていただきたいです。それが、誰かにとって、自分にとっての「あらたな一歩」に続くかもしれません。
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。
小説家
今回のテーマは「あらたな一歩」です。生きていれば、日々の中で辛いことはたくさんあると思います。しかし、生きてさえいれば、誰でも「あらたな一歩」を踏み出すことができる。応募作品を読みながら、そんなことを思いました。
大賞作品と準大賞についてコメントしたいと思います。
「あらたな色」
主人公は不登校の娘をもつ母親です。派手な展開はないですし、最終的にも問題がすべて解決したわけではありません。
しかし、娘も、そして母親も、確実に新たな一歩を踏み始めていました。
優しさと救いのある素晴らしい作品でした。大賞受賞おめでとうございます。
「青いハンカチ」
冒頭の一行から引き込まれました。青いハンカチが、主人公の若き日の恋、夫婦の絆、さらには孫との交流に寄り添い、人間のドラマが詰まっていました。ラストにあたたかな気持ちになるのも心に響きました。
全体を見て、第3回にもなると賞のカラーというものが定着してきたなという印象です。過去2回と比べてカテゴリーエラーだと感じる作品は少なく、穏やかで優しい物語が多かったです。
それはポジティブな感想でもある反面、似た傾向の作品が増えたとも感じています。
そんな中、佳作に選ばれた作品には、少し目先の変わった作品が多かったように思います。
テーマを真正面から表現した作品も、少し遊び心を加えた作品も、どちらも素晴らしく、楽しませていただきました。
応募してくださった皆様、ありがとうございました。作家としても、とても刺激になりました。
選考委員
八木原保
一般社団法人日本メンズファッション協会(MFU)理事長
一般社団法人日本メンズファッション協会(MFU)は「感動創造」を理念に掲げ、事業活動を通じて社会貢献と豊かな生活文化の実現に取り組んでいます。
読者の皆さんの日々が元気になるような作品が集まることを願い「ひなた短編文学賞」を共催しています。
今年は主人公が「あらたな一歩」を踏み出すことに期待し「遠まわりの雛たち」をMFU賞に選びました。
「遠まわりの雛たち」
あらたな一歩には今日の挫折が切っ掛けになるかもしません。「人生万事塞翁が馬」あるいは「禍福は糾える縄の如し」を現実の世界でも実感されている人達は多いことと思います。
本作はそのような哲学的なモチーフにも拘わらず最後にはクスっと笑えるストーリーです。
お楽しみください。
選考委員
伊澤史朗氏
双葉町長
2023 年のフレックスジャパン株式会社ひなた工房の双葉町での開業を記念して創設された「ひなた短編文学賞」が、今年で 3 回目の開催の運びに至ったことを大変嬉しく思っています。
今回も多くの作品が応募され、執筆者の方々ならびに、本文学賞開催に関わったすべての方々に厚く御礼申し上げます。
「どんな色が、好き?」
「ママはね、ピンクが好き」、「ぼくはね、あおかな」という作者とお子さんとのやりとり。作者が若かった頃に世間からの見方に苦しんだ時期。
現在になり、息子さんとの素直な思いを言い合える関係。
好きなものを好きだといえること、それぞれの価値観が認められること、
その大事さを感じる作品でした。
選考委員
太田博久氏
株式会社太田屋 代表取締役社長
第三回ひなた短編文学賞にあたり、僭越ながら「太田屋賞」を設け選考委員を務めることとなりました。この文学賞の根底には「喪失と向き合い未来をつくる」という弊社が営む葬送供養と共通する思いが流れていると感じています。ご応募いただいたすべての作品を拝読し、選考に迷う作品が何点もございましたが、その中から「新しい壁」を受賞作品といたしました。亡き祖父と共に「あらたな一歩」を踏み出そうとする壁装職人の孫の姿を描いたこの作品は、多くのご遺族と接する弊社が、そのお一人お一人に叶えて欲しい姿そのものです。受賞作品をイラストで映像化いたしましたので、ご覧いただけましたら幸いです。(映像化作品は11月末公開予定)
選考委員
蜂賀三月氏
小説家
私たちの生活は「一歩」の連続です。
人の数だけ歩み方があるように、多種多様な作品が届きました。
内容の違いはあれど、どの作品も日向のようなぬくもりがありました。
ひなた短編文学賞の趣旨に寄り添っていただき、本当にありがとうございます。
作品を応募してくれた作家の皆様に、心から感謝を申し上げます。
過去最多となった応募作品の中から、大賞に輝いたのは谷地雪さんの『あらたな色』。
いじめが原因で不登校になった母娘の物語です。作品内で語られる「あらたな一歩」は、人によっては物足りないように感じるかもしれません。それでも、一歩は一歩です。どれだけ進んだかは些細な問題で、本当に大切なのは踏み出す行為そのものにあるように感じました。作品を読んだ人に、踏み出す勇気を与えてくれる傑作です。
続いて、準大賞に選出されたのはウダ・タマキさんの『青いハンカチ』。
ありありと情景が浮かび上がってくる文章に惹かれました。
しっかりと描写・表現されており、文章構成もよく整理されていて、物語が沁み込んでくるようでした。
人生において「あらたな一歩」を踏み出さなければいけない場面は、たくさん存在します。
ときには歩みが止まったり、後退することだってあるでしょう。
そうしたとき、自分のためだけじゃなくて誰かのために前を向こうとする尊さを、この作品が教えてくれました。
さて、第一回、第二回に続き、選考委員という立場で全作品を拝読いたしました。
ひなた短編文学賞は賞の特性上、辛い過去や悩みなど、人の心のセンシティブな部分にフォーカスを当てる作品がよく届きます。それはたくさんの人の痛みに触れるのと同じであり、小説というフィクションだとしても、真摯に向き合う覚悟が必要です。作品を読み進めていくなかで、今回は小説(ひなた短編文学賞)に挑戦する気持ちを題材にした作品がいくつかありました。ある意味メタ的な構造の小説ですが、ひなた短編文学賞自体が誰かの「あらたな一歩」になっていることを感じ、感銘を受けました。同時に、このひなた短編文学賞という文学賞が続いていく意味と意義について、深く考えさせられました。
痛みを受け入れることや、問題を乗り越えること。人や場所、記憶に寄り添うこと。そして、誰かの一歩を見守ること。「あらたな一歩」の形は人それぞれですが、どれも価値のあることです。惜しくも受賞を逃した方々の作品も、素晴らしいものばかりでした。可能ならば、ぜひ投稿サイトなどを活用してたくさんの人に届けていただきたいです。それが、誰かにとって、自分にとっての「あらたな一歩」に続くかもしれません。
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。
一般社団法人日本メンズファッション協会(MFU)理事長
一般社団法人日本メンズファッション協会(MFU)は「感動創造」を理念に掲げ、事業活動を通じて社会貢献と豊かな生活文化の実現に取り組んでいます。
読者の皆さんの日々が元気になるような作品が集まることを願い「ひなた短編文学賞」を共催しています。
今年は主人公が「あらたな一歩」を踏み出すことに期待し「遠まわりの雛たち」をMFU賞に選びました。
「遠まわりの雛たち」
あらたな一歩には今日の挫折が切っ掛けになるかもしません。「人生万事塞翁が馬」あるいは「禍福は糾える縄の如し」を現実の世界でも実感されている人達は多いことと思います。
本作はそのような哲学的なモチーフにも拘わらず最後にはクスっと笑えるストーリーです。
お楽しみください。
選考委員
伊澤史朗氏
双葉町長
2023 年のフレックスジャパン株式会社ひなた工房の双葉町での開業を記念して創設された「ひなた短編文学賞」が、今年で 3 回目の開催の運びに至ったことを大変嬉しく思っています。
今回も多くの作品が応募され、執筆者の方々ならびに、本文学賞開催に関わったすべての方々に厚く御礼申し上げます。
「どんな色が、好き?」
「ママはね、ピンクが好き」、「ぼくはね、あおかな」という作者とお子さんとのやりとり。作者が若かった頃に世間からの見方に苦しんだ時期。
現在になり、息子さんとの素直な思いを言い合える関係。
好きなものを好きだといえること、それぞれの価値観が認められること、
その大事さを感じる作品でした。
選考委員
太田博久氏
株式会社太田屋 代表取締役社長
第三回ひなた短編文学賞にあたり、僭越ながら「太田屋賞」を設け選考委員を務めることとなりました。この文学賞の根底には「喪失と向き合い未来をつくる」という弊社が営む葬送供養と共通する思いが流れていると感じています。ご応募いただいたすべての作品を拝読し、選考に迷う作品が何点もございましたが、その中から「新しい壁」を受賞作品といたしました。亡き祖父と共に「あらたな一歩」を踏み出そうとする壁装職人の孫の姿を描いたこの作品は、多くのご遺族と接する弊社が、そのお一人お一人に叶えて欲しい姿そのものです。受賞作品をイラストで映像化いたしましたので、ご覧いただけましたら幸いです。(映像化作品は11月末公開予定)
選考委員
蜂賀三月氏
小説家
私たちの生活は「一歩」の連続です。
人の数だけ歩み方があるように、多種多様な作品が届きました。
内容の違いはあれど、どの作品も日向のようなぬくもりがありました。
ひなた短編文学賞の趣旨に寄り添っていただき、本当にありがとうございます。
作品を応募してくれた作家の皆様に、心から感謝を申し上げます。
過去最多となった応募作品の中から、大賞に輝いたのは谷地雪さんの『あらたな色』。
いじめが原因で不登校になった母娘の物語です。作品内で語られる「あらたな一歩」は、人によっては物足りないように感じるかもしれません。それでも、一歩は一歩です。どれだけ進んだかは些細な問題で、本当に大切なのは踏み出す行為そのものにあるように感じました。作品を読んだ人に、踏み出す勇気を与えてくれる傑作です。
続いて、準大賞に選出されたのはウダ・タマキさんの『青いハンカチ』。
ありありと情景が浮かび上がってくる文章に惹かれました。
しっかりと描写・表現されており、文章構成もよく整理されていて、物語が沁み込んでくるようでした。
人生において「あらたな一歩」を踏み出さなければいけない場面は、たくさん存在します。
ときには歩みが止まったり、後退することだってあるでしょう。
そうしたとき、自分のためだけじゃなくて誰かのために前を向こうとする尊さを、この作品が教えてくれました。
さて、第一回、第二回に続き、選考委員という立場で全作品を拝読いたしました。
ひなた短編文学賞は賞の特性上、辛い過去や悩みなど、人の心のセンシティブな部分にフォーカスを当てる作品がよく届きます。それはたくさんの人の痛みに触れるのと同じであり、小説というフィクションだとしても、真摯に向き合う覚悟が必要です。作品を読み進めていくなかで、今回は小説(ひなた短編文学賞)に挑戦する気持ちを題材にした作品がいくつかありました。ある意味メタ的な構造の小説ですが、ひなた短編文学賞自体が誰かの「あらたな一歩」になっていることを感じ、感銘を受けました。同時に、このひなた短編文学賞という文学賞が続いていく意味と意義について、深く考えさせられました。
痛みを受け入れることや、問題を乗り越えること。人や場所、記憶に寄り添うこと。そして、誰かの一歩を見守ること。「あらたな一歩」の形は人それぞれですが、どれも価値のあることです。惜しくも受賞を逃した方々の作品も、素晴らしいものばかりでした。可能ならば、ぜひ投稿サイトなどを活用してたくさんの人に届けていただきたいです。それが、誰かにとって、自分にとっての「あらたな一歩」に続くかもしれません。
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。
双葉町長
今回も多くの作品が応募され、執筆者の方々ならびに、本文学賞開催に関わったすべての方々に厚く御礼申し上げます。
「どんな色が、好き?」
「ママはね、ピンクが好き」、「ぼくはね、あおかな」という作者とお子さんとのやりとり。作者が若かった頃に世間からの見方に苦しんだ時期。 現在になり、息子さんとの素直な思いを言い合える関係。
好きなものを好きだといえること、それぞれの価値観が認められること、 その大事さを感じる作品でした。
選考委員
太田博久氏
株式会社太田屋 代表取締役社長
第三回ひなた短編文学賞にあたり、僭越ながら「太田屋賞」を設け選考委員を務めることとなりました。この文学賞の根底には「喪失と向き合い未来をつくる」という弊社が営む葬送供養と共通する思いが流れていると感じています。ご応募いただいたすべての作品を拝読し、選考に迷う作品が何点もございましたが、その中から「新しい壁」を受賞作品といたしました。亡き祖父と共に「あらたな一歩」を踏み出そうとする壁装職人の孫の姿を描いたこの作品は、多くのご遺族と接する弊社が、そのお一人お一人に叶えて欲しい姿そのものです。受賞作品をイラストで映像化いたしましたので、ご覧いただけましたら幸いです。(映像化作品は11月末公開予定)
選考委員
蜂賀三月氏
小説家
私たちの生活は「一歩」の連続です。
人の数だけ歩み方があるように、多種多様な作品が届きました。
内容の違いはあれど、どの作品も日向のようなぬくもりがありました。
ひなた短編文学賞の趣旨に寄り添っていただき、本当にありがとうございます。
作品を応募してくれた作家の皆様に、心から感謝を申し上げます。
過去最多となった応募作品の中から、大賞に輝いたのは谷地雪さんの『あらたな色』。
いじめが原因で不登校になった母娘の物語です。作品内で語られる「あらたな一歩」は、人によっては物足りないように感じるかもしれません。それでも、一歩は一歩です。どれだけ進んだかは些細な問題で、本当に大切なのは踏み出す行為そのものにあるように感じました。作品を読んだ人に、踏み出す勇気を与えてくれる傑作です。
続いて、準大賞に選出されたのはウダ・タマキさんの『青いハンカチ』。
ありありと情景が浮かび上がってくる文章に惹かれました。
しっかりと描写・表現されており、文章構成もよく整理されていて、物語が沁み込んでくるようでした。
人生において「あらたな一歩」を踏み出さなければいけない場面は、たくさん存在します。
ときには歩みが止まったり、後退することだってあるでしょう。
そうしたとき、自分のためだけじゃなくて誰かのために前を向こうとする尊さを、この作品が教えてくれました。
さて、第一回、第二回に続き、選考委員という立場で全作品を拝読いたしました。
ひなた短編文学賞は賞の特性上、辛い過去や悩みなど、人の心のセンシティブな部分にフォーカスを当てる作品がよく届きます。それはたくさんの人の痛みに触れるのと同じであり、小説というフィクションだとしても、真摯に向き合う覚悟が必要です。作品を読み進めていくなかで、今回は小説(ひなた短編文学賞)に挑戦する気持ちを題材にした作品がいくつかありました。ある意味メタ的な構造の小説ですが、ひなた短編文学賞自体が誰かの「あらたな一歩」になっていることを感じ、感銘を受けました。同時に、このひなた短編文学賞という文学賞が続いていく意味と意義について、深く考えさせられました。
痛みを受け入れることや、問題を乗り越えること。人や場所、記憶に寄り添うこと。そして、誰かの一歩を見守ること。「あらたな一歩」の形は人それぞれですが、どれも価値のあることです。惜しくも受賞を逃した方々の作品も、素晴らしいものばかりでした。可能ならば、ぜひ投稿サイトなどを活用してたくさんの人に届けていただきたいです。それが、誰かにとって、自分にとっての「あらたな一歩」に続くかもしれません。
株式会社太田屋 代表取締役社長
第三回ひなた短編文学賞にあたり、僭越ながら「太田屋賞」を設け選考委員を務めることとなりました。この文学賞の根底には「喪失と向き合い未来をつくる」という弊社が営む葬送供養と共通する思いが流れていると感じています。ご応募いただいたすべての作品を拝読し、選考に迷う作品が何点もございましたが、その中から「新しい壁」を受賞作品といたしました。亡き祖父と共に「あらたな一歩」を踏み出そうとする壁装職人の孫の姿を描いたこの作品は、多くのご遺族と接する弊社が、そのお一人お一人に叶えて欲しい姿そのものです。受賞作品をイラストで映像化いたしましたので、ご覧いただけましたら幸いです。(映像化作品は11月末公開予定)
選考委員
蜂賀三月氏
小説家
私たちの生活は「一歩」の連続です。
人の数だけ歩み方があるように、多種多様な作品が届きました。
内容の違いはあれど、どの作品も日向のようなぬくもりがありました。
ひなた短編文学賞の趣旨に寄り添っていただき、本当にありがとうございます。
作品を応募してくれた作家の皆様に、心から感謝を申し上げます。
過去最多となった応募作品の中から、大賞に輝いたのは谷地雪さんの『あらたな色』。
いじめが原因で不登校になった母娘の物語です。作品内で語られる「あらたな一歩」は、人によっては物足りないように感じるかもしれません。それでも、一歩は一歩です。どれだけ進んだかは些細な問題で、本当に大切なのは踏み出す行為そのものにあるように感じました。作品を読んだ人に、踏み出す勇気を与えてくれる傑作です。
続いて、準大賞に選出されたのはウダ・タマキさんの『青いハンカチ』。
ありありと情景が浮かび上がってくる文章に惹かれました。
しっかりと描写・表現されており、文章構成もよく整理されていて、物語が沁み込んでくるようでした。
人生において「あらたな一歩」を踏み出さなければいけない場面は、たくさん存在します。
ときには歩みが止まったり、後退することだってあるでしょう。
そうしたとき、自分のためだけじゃなくて誰かのために前を向こうとする尊さを、この作品が教えてくれました。
さて、第一回、第二回に続き、選考委員という立場で全作品を拝読いたしました。
ひなた短編文学賞は賞の特性上、辛い過去や悩みなど、人の心のセンシティブな部分にフォーカスを当てる作品がよく届きます。それはたくさんの人の痛みに触れるのと同じであり、小説というフィクションだとしても、真摯に向き合う覚悟が必要です。作品を読み進めていくなかで、今回は小説(ひなた短編文学賞)に挑戦する気持ちを題材にした作品がいくつかありました。ある意味メタ的な構造の小説ですが、ひなた短編文学賞自体が誰かの「あらたな一歩」になっていることを感じ、感銘を受けました。同時に、このひなた短編文学賞という文学賞が続いていく意味と意義について、深く考えさせられました。
痛みを受け入れることや、問題を乗り越えること。人や場所、記憶に寄り添うこと。そして、誰かの一歩を見守ること。「あらたな一歩」の形は人それぞれですが、どれも価値のあることです。惜しくも受賞を逃した方々の作品も、素晴らしいものばかりでした。可能ならば、ぜひ投稿サイトなどを活用してたくさんの人に届けていただきたいです。それが、誰かにとって、自分にとっての「あらたな一歩」に続くかもしれません。
小説家
人の数だけ歩み方があるように、多種多様な作品が届きました。
内容の違いはあれど、どの作品も日向のようなぬくもりがありました。
ひなた短編文学賞の趣旨に寄り添っていただき、本当にありがとうございます。
作品を応募してくれた作家の皆様に、心から感謝を申し上げます。
過去最多となった応募作品の中から、大賞に輝いたのは谷地雪さんの『あらたな色』。
いじめが原因で不登校になった母娘の物語です。作品内で語られる「あらたな一歩」は、人によっては物足りないように感じるかもしれません。それでも、一歩は一歩です。どれだけ進んだかは些細な問題で、本当に大切なのは踏み出す行為そのものにあるように感じました。作品を読んだ人に、踏み出す勇気を与えてくれる傑作です。
続いて、準大賞に選出されたのはウダ・タマキさんの『青いハンカチ』。
ありありと情景が浮かび上がってくる文章に惹かれました。
しっかりと描写・表現されており、文章構成もよく整理されていて、物語が沁み込んでくるようでした。
人生において「あらたな一歩」を踏み出さなければいけない場面は、たくさん存在します。
ときには歩みが止まったり、後退することだってあるでしょう。
そうしたとき、自分のためだけじゃなくて誰かのために前を向こうとする尊さを、この作品が教えてくれました。
さて、第一回、第二回に続き、選考委員という立場で全作品を拝読いたしました。
ひなた短編文学賞は賞の特性上、辛い過去や悩みなど、人の心のセンシティブな部分にフォーカスを当てる作品がよく届きます。それはたくさんの人の痛みに触れるのと同じであり、小説というフィクションだとしても、真摯に向き合う覚悟が必要です。作品を読み進めていくなかで、今回は小説(ひなた短編文学賞)に挑戦する気持ちを題材にした作品がいくつかありました。ある意味メタ的な構造の小説ですが、ひなた短編文学賞自体が誰かの「あらたな一歩」になっていることを感じ、感銘を受けました。同時に、このひなた短編文学賞という文学賞が続いていく意味と意義について、深く考えさせられました。
痛みを受け入れることや、問題を乗り越えること。人や場所、記憶に寄り添うこと。そして、誰かの一歩を見守ること。「あらたな一歩」の形は人それぞれですが、どれも価値のあることです。惜しくも受賞を逃した方々の作品も、素晴らしいものばかりでした。可能ならば、ぜひ投稿サイトなどを活用してたくさんの人に届けていただきたいです。それが、誰かにとって、自分にとっての「あらたな一歩」に続くかもしれません。